カリブ海、アフリカ、ヨーロッパのリズムを融合させたラテン・ジャズは、常に進化し続ける音楽的融合体である。その歩みを更に推し進めてきたのがチューチョ・バルデスのようなピアニストだ。彼は1973年にハバナで結成したフュージョン・グループ、イラケレを通じてキューバ音楽に革命をもたらし、1990年代にはブルーノートの一員となった。
その偉大なチューチョ・バルデス、そして同じくブルーノートに名を刻むもう一人の偉大なキューバ人ピアニスト、ゴンサロ・ルバルカバの足跡を辿るのが、ハバナ出身のアロルド・ロペス=ヌッサである。彼はこう語っている。「チューチョとゴンサロは私にとって参照点であり、また大きなインスピレーションなんだ。ブルーノートで彼らの後を追えることは祝福に他ならない。ただ、自分をその継承者と名乗るにはあまりに重すぎる」
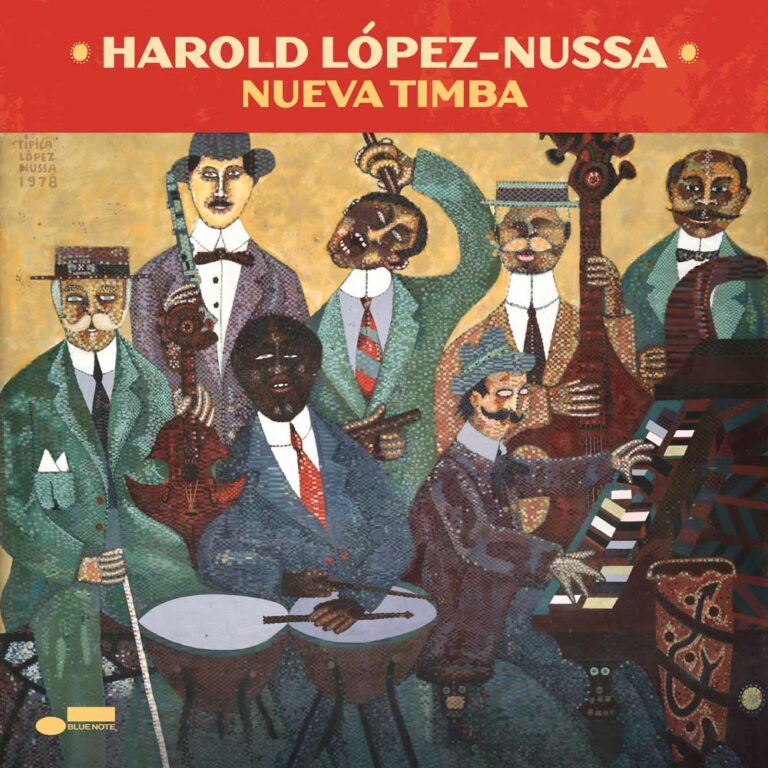
アロルド・ロペス=ヌッサ Nueva Timba
Available to purchase from our US store.2021年より南フランスのトゥールーズで家族と共に暮らすロペス=ヌッサは、マック・アヴェニュー・レーベルから一連のアルバム・リリースを経て、2023年にブルーノートと契約し、境界を押し広げる作品『Timba A La Americana』を、そして2年後の現在、彼はその革新的な続編『Nueva Timba』をリリースした。本作はパリのデュック・デ・ロンバールでのライヴ録音を基盤とし、スタジオでロペス=ヌッサ自身の手によって再構築され、磨き上げられたものである。「ハバナの祖母の家で、初めてブルーノートのアナログ盤を聴いたことを覚えている。だから自分がそのレーベルにいることは夢が叶ったような気分で、いまだ信じられないよ」と彼は語る。
アロルド・ロペス=ヌッサは、文化的に活気あるハバナのベダード地区において、音楽に深く根差した家庭で育った。「祖母はピアニストで、母もまたピアノ教師(故マイラ・トーレス)でピアニストだったんだ。そして父はドラマー(ルイ・ロペス=ヌッサ)だったよ」と彼は述懐する。「私と兄(初期から共にドラムを叩いてきた)は、そのような環境の中で育った。それは私たちにとってごく自然なことだったんだ」
彼の2作のブルーノート作品はいずれも、ハバナの根深い音楽生活からトゥールーズへと家族と共に移住した後に録音されたものである。彼は言う。「ハバナは音楽に溢れている。コンサートやルンバのセッション、友人たちとのジャムなど、常に音楽が周囲にある。だから環境の変化について行くのは大変だったよ。最初の一年は本当に苦しかった。なぜなら自分がここに属しているという実感を全く持てなかったのだから」
故郷への郷愁に加え、移住はロペス=ヌッサにとって、生まれ育った祖国の音楽を初めて外側から見つめ直す契機ともなった。「ブルーノートと契約した時、私は従来の自分の視点とは全く異なる形でキューバ音楽を取り入れたいと考えていた」と彼は語る。「多くのことを実験したいと思っていたが、その試みに対してブルーノートの社長ドン・ウォズが完全な自由を与えてくれたんだ」

慣習の枠を打ち破るために、ロペス=ヌッサはスナーキー・パピーのマイケル・リーグをプロデューサー兼共同作曲者として招いた。「マイケルとは数年来の友人で、まずアイデアを語り合い、バンド(ドラム=ルイ・アドリアン・ロペス=ヌッサ、ハーモニカ=グレゴア・マレ、ベース=ルケス・カーティス、コンガ=バルバロ“マチート”クレスポ、シンセサイザー=マイケル・リーグ)と共にスタジオに入ったんだ」とロペス=ヌッサは語る。「その後、マイケルがさらに自分の要素を加えてくれた。音楽が進化していくのを聴くのは本当にエキサイティングで、その経験がスタジオの可能性に対する自分の視野を大きく開いてくれたよ」
2023年にリリースされた『Timba A La Americana』は、トゥールーズ移住から2年後に発表された作品であり、ラテン・ジャズに新たな生命を吹き込んだ。ロペス=ヌッサはこのアルバムで初めてキーボードを演奏し、リーグと共にキューバ音楽の古典的クラーベ・パターンを現代的なエレクトロニクスとスタジオ実験の脈動を通じて再解釈したのである。「伝統を大いに尊重しながら、他ジャンルの影響やリズム、ハーモニーを融合させることが自分の目標なんだ」とロペス=ヌッサは続ける。「ただし、これを実現するには時間がかかる。なぜならキューバ音楽と文化は非常に豊かであり、新しいことに挑む前に学ぶべきことが数多く存在するからね」
当初『Nueva Timba』は、パリのデュック・デ・ロンバールでの3夜のライヴ録音をそのまま収めたアルバムとして企画されていた。兄ルイ・アドリアン・ロペス=ヌッサ(ドラム)、ルケス・カーティス(ベース)、そしてハーモニカの名手グレゴア・マレと共演したものであった。しかしロペス=ヌッサはスタジオでの覚醒を受け、この作品を別の音響的方向へと導いたのである。「マイケルとの経験は、この新しいアルバムにおける自分の指針となった」と彼は語る。「3夜のライヴであまりに多くの素材が残ったので、それを分解し、さらに何かを加えてみてはどうかと考え始めた。スタジオに入ってからはローズ・ピアノや新しい音色、クレイジーなエフェクトを重ね、さらに自宅のコンピュータで多くの作業をした。本当に多様な要素の混合体に仕上がったよ」
『Nueva Timba』には、ロペス=ヌッサ自身の作品「Cerca y Lejo」のような強烈なフュージョン曲に加え、ベニー・モレーの「Bonito y Sabroso」の現代的な再解釈が収録されている。1950年代のビッグバンド・クラシックを、今日的なサイケ風味を纏った重厚なラテン・ジャズへと変貌させたのである。「私はベニー・モレーが大好きなんだ。彼の音楽、思考、精神、その全てを。そしてこの曲は特にお気に入りの一つだった」とロペス=ヌッサは語る。「グループで演奏し始め、毎晩のようにアレンジを変え、スタジオに持ち込んで実験を重ねた。本当に楽しい挑戦だったよ」
キューバのスタンダード曲「エル・マニセロ」の再解釈にも、他の音響的革新が見受けられる。「このアルバムでは、スタジオでのミックス方法や、そこから得られる様々なヴァイブレーションといった実験的な要素に非常に興味を持っていた」とロペス=ヌッサは語る。「このアルバムでは、まるで古いラジオ局から流れてくるような音楽にしたいと思ったんだ」
また注目すべき曲は「Niño Con Violin」である。これはハロルドの叔父であり、アフロクーバの創設者でピアニストのエルナン・ロペス=ヌッサの作品で、ハロルドとバンドが全力で演奏している。「コンサートでは常に叔父の曲を取り上げており、2枚のアルバムにも収録しているんだ」とハロルドは語る。「兄とは初期からドラムで共演してきたので、家族的な要素は自分の活動全てに通底している。そして今やこのバンドもまた家族のような存在になった。私たちは大の友人であり、それは私にとって非常に大切なことなんだ」
アコーディオン奏者ヴィンセント・ペイラニが作曲した「Alma y Fuego」に彼を加えたことで、この音楽一家はリーダー同様、オープンな姿勢を示している。「一緒に演奏する時は本当に特別な時間なんだ。彼らは常に何か違うことをしたいと考えているので、それが私にとって本当に刺激的で、その火は絶やさないようにしている」と彼は語る。これらはロペス=ヌッサが未知の領域に挑戦するきっかけにもなっている。「このアルバムでは、事前に深く考えずに多くの実験を行ったんだ」と彼は説明する。「ただアイデアを探し、試行錯誤を繰り返す。これだけさ」
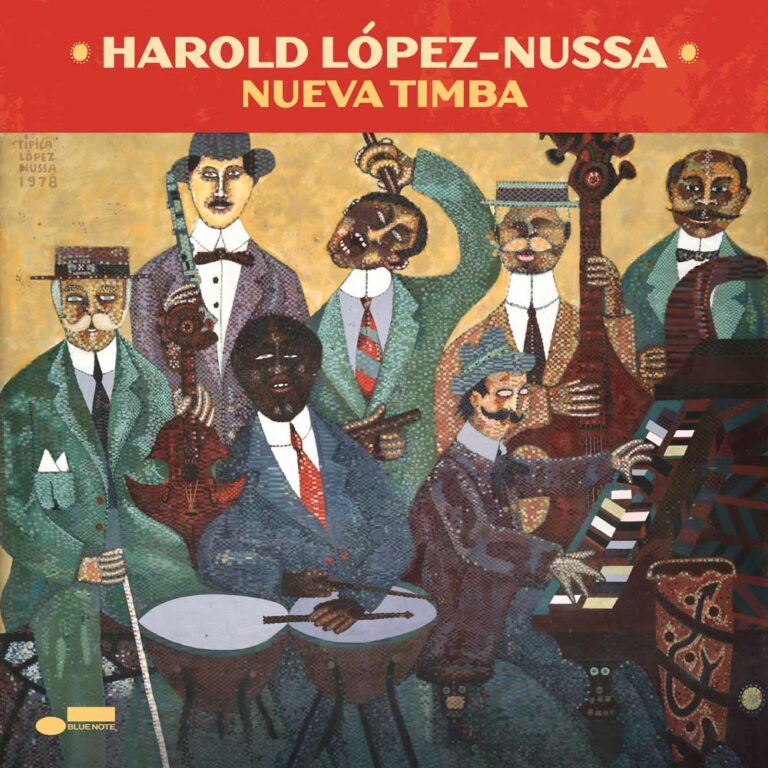
アロルド・ロペス=ヌッサ Nueva Timba
Available to purchase from our US store.アンディ・トーマスはロンドンを拠点とするライターで、Straight No Chaser、Wax Poetics、We Jazz、Red Bull Music Academy、Bandcamp Dailyなどに定期的に寄稿している。また、Strut、Soulのライナーノーツも執筆。
ヘッダー画像: Ryan McNurney / Blue Note Records.


